清少納言の代表作である枕草子。第一弾の冒頭「春はあけぼの~」からはじまり、春夏秋冬を順に述べていきます。ここでは、冬の項の全文と意味を解説していきたいと思います。
-
- 冬はつとめての全文と意味、現代語訳
- 原文
- 現代語訳
- 冬はつとめては何時のこと?
- 春はあけぼのとどっちが早い時間なの?
- 春はあけぼの夏は夜秋は夕暮れの全文と意味
- 原文
- 現代語訳
- 「清少納言の枕草子」と「紫式部の源氏物語」の関係性
- まとめ
- 冬はつとめての全文と意味、現代語訳
冬はつとめての全文と意味、現代語訳
まずは原文を見てみましょう。
原文
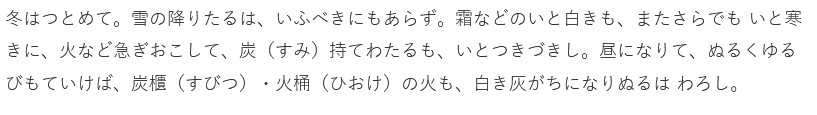
出典元:ORIGAMI
続いて、現代語訳です。
現代語訳
冬は早朝が趣があってよい。
雪が降っている朝はもちろんのこと、霜が白い朝もよい。またそうでなくとも、とても寒い朝に火を急いでおこして炭を持って運びまわるのも、しっくりくる。
しかし、昼になって寒さがやわらぐ頃には、火桶の灰に白い灰が増えてしまい、もうあまり趣きを感じない。
冬はつとめては何時のこと?
全文の現代語訳でも触れましたが、「冬はつとめて」は冬の早朝を指します。

出典元:朝日新聞デジタル
清少納言は四季のそれぞれについて、素晴らしいと感じる時間帯を挙げて、趣深く情景を描きました。
春はあけぼのとどっちが早い時間なの?
四季それぞれで、清少納言が題材としている時間帯をみてみましょう。
春はあけぼの:現代語訳は「春は明け方がよい」という意味です。
明け方とは夜空がうっすら明るくなってくるころを指しており、日の出前を指します。

出典元:ウェザーニュース
つまり、冬よりも春の方が早い時間帯のお話ということです。
「夏は夜」「秋は夕暮れ」については説明は不要ですね!
春はあけぼの夏は夜秋は夕暮れの全文と意味
せっかく冬の項をご紹介したので、よろしければ他の季節の原文と現代語訳も味わってみてください。
原文
まずは原文です。
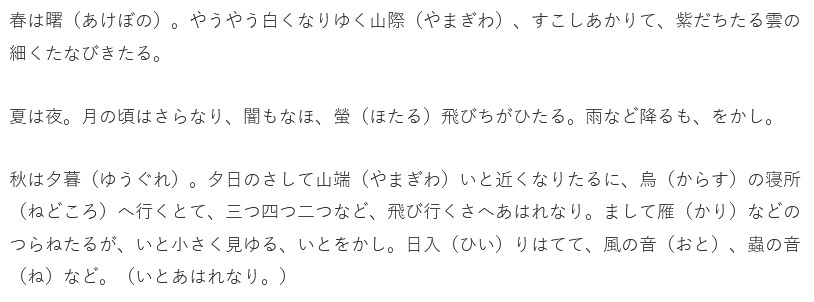
出典元:ORIGAMI
続いて現代語訳です。
現代語訳
春は明け方が趣があってよい。
徐々に白くなっていく山の稜線が少し明るくなって、紫がかった雲が、細く揺れ動いているのがよい。

出典元:tenki.jp
夏は夜が趣があってよい。
月が明るい頃は言うまでもないが、月の無い闇夜にほたるが多く飛んでいる様子もよい。
1,2匹がぼんやりと光って飛んでいるのも趣がある。雨が降るのもよい。

出典元:Toshiba Clip
秋は夕暮れが趣があってよい。
夕日が差して山の端近くに沈んだ頃、カラスが寝ぐらへ帰ろうとして、3羽4羽、2羽3羽と飛び急ぐ様子も趣がある。
ましてやカリ(現代のガン。大型の水鳥の総称)が連なって小さく見えるのは、とても趣がある。
日が暮れて、風の音や虫の音が聞こえるのも、言うまでもなくよい。

出典元:世界の民謡・童謡
それぞれの季節において、素敵な情景がありありと目に浮かぶようですね。
番外編
ちなみに、秋の項で登場した雁は近くで見ると、こういう鳥です。

出典元:語源由来辞典
見たことがあるような無いような、ですかね!昭和の時代までは多くみることができたようです。冬にツバメと入れ違いにロシアからやってくる渡り鳥です。当時は食用にもされたようですが、個体数の減少によって近年は狩猟は禁じられています。
「清少納言の枕草子」と「紫式部の源氏物語」の関係性
言うまでもなく、清少納言の枕草子は平安時代の日本文学の代表作の一つであり、日本三大随筆の一つです。おおよそ長保3年(1001年)には完成したとされています。
枕草子は藤原定子の女房として仕えた宮中での生活や、日常のできごとを随筆しています。今回取り上げたのは第1弾のみでしたが、実は約300に及ぶ章段で構成されています。
現代風の言い方をすると、ポエムやエッセイといった趣でしょうか。清少納言の豊かな感性と恵まれた知性を感じられる内容に仕上がっています。
一方で、数年後に出てくることになる紫式部の「源氏物語」は、現代に強引に置き換えると、重厚なストーリーを持った2時間ドラマや同人誌といった趣もあります。
そのあたりのタイプの違い故か、紫式部からは「紫式部日記」で手痛い批評を加えられています。まぁ、同時代を生きる天才女性作家の2人ですから、ライバル心があってもおかしくはないですね!
冬はつとめての意味と全文、現代語訳のまとめ
冬はつとめては、冬の早朝のことを指します。
夜明け前の「春はあけぼの」より少しだけ遅れた時間帯を指しています。
平安時代に執筆された文章とはいえ、現代人が読んでも情景がありありと浮かび、臨場感がありますね。


